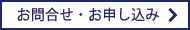本県教員採用試験を知る
教員採用試験は各地方公共団体で試験問題が違います。その為、市販の問題集を活用しても解けない問題が多々あります。本県教員採用試験の特徴としてまず挙げられるのは、試験合格倍率が非常に高いということです。例年、全国1、2を争う倍率となり、特に高等学校受験者においての合格は狭き門となっております。
一般教養試験においては社会科学と自然科学で全体の約3分の2を占めます。沖縄に特化した問題として、琉球・沖縄の歴史、文化等が毎年出題されていて、今後もその傾向は変わらないでしょう。
教職教養試験において注目したいのは本県の教育重要施策が毎年かなりの配点で出題されていることです。このことから、沖縄県教育委員会が策定・作成している学校教育施策に関する資料は今後もかなりの確率で出題の可能性があるとみてよいでしょう。特に最近の教育施策は要チェックです。又、例年、各校種の学習指導要領解説総則編からの出題が多くありますが、2023年実施試験では小学校学習指導要領解説特別活動編や特別支援学校教育要領・学習指導要領解説総則編からも出題されています。学習指導要領の出題範囲が広がったことから、早期に学習指導要領に関する対策を実施する必要があります。
二次試験は教科によって実技試験がある教科もありますが、個人面接、模擬授業は必須です。二次試験においては個人面接のような人物試験が特に重視されます。教師という職業は、児童生徒の前に立ち、模範となったり、指導したりする立場にある。その為、教師自身の人間性は、児童生徒の人間形成に大きな影響を与えるものである。それゆえ、特に近年の教員採用試験では“人物評価”を重視する面接による選考が採用合否のキーポイントになっています。教育基本法の第1条にもありますように、「人格の完成を目指す」ことを職務とする人(教育者)を選ぼうとする場面ですから、人物重視の考えは十分に納得できると思います。
模擬授業は教科の一部を実際に授業してもらうもので、時間は分5から12分程度、導入の部分が一般的でしたが、最近は展開やまとめ(振り返りを含む)も、教科によっては授業課題となっています。さらに、模擬授業後にいくつかの質問が試験官からあります。指導内容以上に、与えられた時間内にどれだけ児童生徒を大切にした授業をしようとしたか、また、「指導と評価の一体化」の観点からどう授業が構成されているかがポイントとなります。それだけに受験者は「授業力」「評価からの授業改善」の視点を身に付ける練習を十分にしておくことが必要です。
まなび道では学校現場同様の黒板も設置していますので、効率的に活用し、模擬授業対策が行えます。
以上、本県の教員採用試験の教養試験と二次試験について特徴を説明しましたが、一次試験では各校種教科の専門試験も実施されます。まなび道では小学校全科試験対策を講座開講していて毎年多くの合格者を輩出していますが、一部の教科を除き、その他の専門試験対策も充実しています。計画的、継続的な対策で教養試験70点以上、専門試験8割、二次試験では効率的かつ独自性を求めた対策を行い、全員合格を目指します。